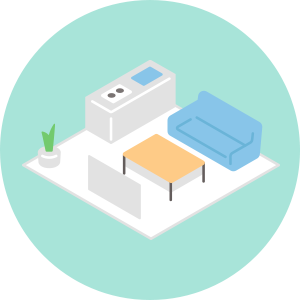初めてでも安心! 洋食のテーブルマナーの基本について
洋食は特別なディナーや結婚披露宴、ビジネスの会食など、フォーマルな場で登場することが多い料理スタイルです。
ナイフやフォークを使った食事に慣れていないと、ふとした瞬間に「これって正しいのかな」と不安になる人も少なくありません。
そこで今回は、洋食の席で困らないように、基本的なマナーを解説します。
ナイフとフォークの持ち方
洋食の席では、料理そのものの味わいや雰囲気だけでなく、テーブルマナーがその人の印象を大きく左右します。
特にナイフとフォークの扱い方は最も目につきやすい部分で、誤った持ち方をしていると「食べ慣れていない」、「所作が乱雑」という印象を与えてしまうことがありますが、正しい持ち方と扱い方を身につけておくと、上品で落ち着いた振る舞いができます。
ナイフは右手に持ち、フォークは左手に持つのが基本で、ナイフは柄の部分を親指と人差し指で軽くつまみ、中指で支えるように保持します。
強く握りしめるのではなく、ペンを持つときのようにしなやかに扱い、食材を切る際には力任せに押しつけるのではなく、滑らせるように動かすと美しく見えます。
フォークは背を下に向け、柄は手のひらに深く入れず、ナイフと同様に親指と人差し指で軽く支え、中指で安定させると扱いやすく、ナイフで切った一口大の食材をそのまま口へ運びましょう。
ナイフとフォークの置き方マナー
ナイフ、フォーク、スプーンは「カトラリー」と呼ばれ、洋食のテーブルマナーにおいて、その置き方は周囲やサービスを担当するスタッフに意思を伝える大切なサインになります。
食事中の合図
食事の途中で一時的に手を止めたいときは、ナイフとフォークを「八の字」にして皿の上に置くのが基本で、フォークの背を下に向けて皿の左側に、ナイフの刃先を内側に向けて皿の右側に置き、先端が皿の中央あたりで交わる形にします。
国や文化によってフォークとナイフの柄を皿の外側に少し広げる、フォークとナイフを軽く交差させるなどスタイルが若干異なりますが、「食事を続けます」というサインに変わりはありません。
食事終了の合図
食べ終わったことを伝えるときは、ナイフとフォークを揃えて皿の右下に斜めに置きます。
フォークの背は下にするのが基本で、バラバラに置いてしまうと「まだ使うかもしれない」と解釈される場合があるため、食べ終わりの合図は正しく示しましょう。
ナプキンの使い方
洋食の席におけるナプキンの扱いは、カトラリーの使い方と同じくらい周囲からよく見られているマナーのひとつです。
最初に膝の上に置く
席に着いたら、料理が運ばれる前にナプキンを広げて半分に二つ折りにして膝の上に置くのが基本です。
折り目が自分側に来るようにすると、使用時に内側を自然に使えます。
ナプキンを首にかけたり丸めて置いたりするのは、家庭的な食事や子ども用に限定され、フォーマルな場では失礼にあたります。
また、テーブルの上に最初から置きっぱなしにするのも避けましょう。
ナプキンは、食事が始まる合図として扱うため、主催者や目上の人が広げてから自分も広げると一層丁寧です。
口元を拭くタイミング
食事中にソースや油が口元についたとき、またはワインを飲む前に口を整えたいときにナプキンを使います。
内側で軽く押さえるのが基本で、強くこすったり大きな動作で拭いたりせずに、自然な仕草でさりげなく行うことが大切です。
ナプキンを使用する際には、折り目の内側を使い、使い終わった部分が外から見えないように工夫すると清潔感が保たれます。
席を立つとき、食事を終えるとき
食事の途中で一時的に席を立つ場合は、ナプキンを椅子の上に置く方法が広く用いられています。
食事が終わったら軽くたたんでテーブルの上に置きましょう。
きっちりと畳んでしまうと「また使える状態に戻した」と解釈されてしまうこともあるので、あえて軽く折り畳む程度がスマートで理想的です。
パンとバターの食べ方とスープの飲み方
洋食のテーブルで提供されるパンは、日本の食卓でイメージする「主食」ではなく、料理を引き立てる「添えもの」としての役割を持ちます。
パンを食べるときの基本動作
パンは一口大に手でちぎってから食べるのが原則です。
これはパンが持つ柔らかさや香りを損なわないためでもあり、音を立てたりパンくずが散らかったりするのを防ぐ意味もあります。
ちぎる際は、自身の皿の上で静かに行い、机の上やクロスにパンくずを散らさないように配慮し、口に運ぶたびに少しずつちぎるのがスマートです。
バターの取り方と塗り方
パンに添えられているバターは、共用のバターディッシュから直接パンにつけるのではなく、専用のバターナイフを使って自身のパン皿に取り分けてから使うのが衛生面の配慮であり、マナーです。
取り分けたバターはパン全体にまとめて塗らず、一口サイズにちぎったパンに少しずつ塗って食べるのが望ましい作法になります。
日本人の感覚では「最初に全部塗ってから食べたい」と思うかもしれませんが、フォーマルな洋食では、一口ごとに必要な分を塗る方が上品です。
スープの作法
日本の食文化では茶碗の汁物を自身に引き寄せて口に運ぶため、無意識に「奥から手前へ」動かしてしまいがちですが、洋食でスープをすくう際は「手前から奥へ」が基本です。
奥へすくうことで衣服やテーブルクロスにこぼれるリスクを減らし、動作が自然に見えるのが主な理由で、スプーンには決して山盛りにすくわず、半分から7割程度に抑えるのが美しく見えるコツです。
魚料理、肉料理の食べ方
洋食のコース料理において、魚料理と肉料理はメインディッシュとして位置づけられ、テーブルマナーが最も目につきやすい場面です。
魚料理
魚料理では、骨付きの魚や甲殻類など、見た目が華やかでありながら食べ方に注意を要する料理が多く提供されます。
骨付きの白身魚のソテーやポワレが出された場合、まずはナイフとフォークで上身を切り分けて食べるのが基本で、食べ進めたら、中骨をナイフでそっと外側に寄せ、下身を食べます。
魚をひっくり返さずにナイフとフォークで骨を外して食べるのがスマートで、小骨が出てきた場合は、フォークに軽く乗せて皿の端に置きましょう。
肉料理
肉料理は洋食マナーの中心ともいえる部分で、カトラリーの扱い方が試されます。
基本はナイフで一口大に切り、切ったらそのまま口へ運ぶという流れで、最初に全部切ってしまうのは避けましょう。
切るときは力任せにせず、ナイフを滑らせるように動かしてフォークで押さえ、音を立てずにスムーズな動作で行うことです。
また、ソースのかかった肉料理では、パンでソースを拭って食べても良いとされていますが、高級レストランでは避けるなど、周囲の雰囲気に合わせるようにしましょう。
ワインや飲み物のマナー

洋食の場で提供される飲み物は、喉を潤すためだけのものではなく、料理とのペアリングを意識した上で提供されるため、飲み方やグラスの扱いにマナーが求められます。
グラスの持ち方
ワイングラスを持つときは脚(ステム)の部分を持つのが基本です。
器(ボウル)部分を直接つかむと体温でワインの温度が変わってしまい、香りや味わいに影響を与えます。
また、指紋が目立つのを避けるために、大ぶりのグラスでも手のひらで包み込まず、ステムを持って軽く支えるようにすると上品に見えます。
乾杯のマナー
乾杯の際、日本ではグラスをしっかり当てて音を鳴らす習慣がありますが、洋食の場では避けましょう。
グラスは薄く繊細な作りが多いため破損のリスクがあると同時に、音を立てること自体が無作法ともされており、グラスを軽く掲げるだけ、もしくは目線を合わせて軽く会釈する程度がスマートです。
ワインの飲み方
ワインは一気に飲み干すものではなく、少しずつ口に含んで香りや味を楽しむのがマナーです。
飲むタイミングは料理と一緒に楽しむのが基本で、料理の一口ごとに少量のワインを合わせることで風味が引き立ちます。
洋食マナーは相手への気配り

洋食のテーブルマナーは、同席している人が心地よく過ごせるようにするための気配りで、一つひとつの所作には「相手に不快感を与えない」、「料理を美しく味わう」という意図が込められています。
ビジネスの接待やフォーマルな会食の場ではもちろん、プライベートの食事でも落ち着いた振る舞いができれば、食事がより楽しい時間になるでしょう。

コーチングは現在、ビジネスの場面をはじめ、プライベートの場面においても広く用いられるようになってきています。
それは、コーチングが人の「強み」を伸ばし、行動化をサポートする新しいコミュニケーションの技術であることが理由かもしれません。この技術の新しさは、相手の不平や不満という負の感情さえも、建設的な力への転化が可能であることです。
さらに注目したい画期的な効果として、コーチングが「違い」を活かし合う創造的なコミュニケーションの手法であることから、
相性や性格、価値観が合わない相手との対応力を向上させることも可能にしてしまう点です。
結果として、自分のコミュニケーション能力の飛躍的な向上やリーダーシップなどの幅を広げることに役立てられます。
コーチングは「自分らしさ」も「相手らしさ」も大切にし、「お互いを高め合う」コミュニケーションの手法ともいえます。
老若男女、職種などに関係なく学習し、さまざまな場面で活用できる技術です。