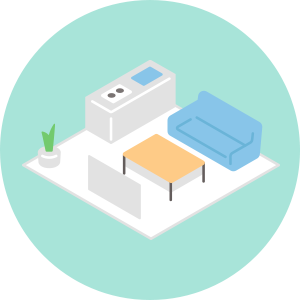今さら聞けない?! 和食マナーの基本について
「和食」は世界に誇る日本の食文化ですが、正しい食事のマナーについては「実はよく知らない」という方も多くいらっしゃいます。
冠婚葬祭やビジネスの接待、会食の場などで「これって合っているのかな」と不安になることがないよう、事前に知識を身につけておき、いざという時にきちんと振る舞えるようにしておきましょう。
今回は、押さえておきたい和食の基本マナーについて、分かりやすく解説します。
お箸の正しい使い方
お箸は日常的に使っているからこそ、正しい使い方を知らないまま食事をしている方も少なくありません。まずは、箸の持ち上げ方と扱い方を確認しましょう。
お箸の持ち上げ方は以下の手順となります。
1.右手でお箸の中央を持つ
2.お箸を下から左手で支えて、右手を右横へ滑らせる
3.右手を返してお箸の上から1/3あたりを持つ
4.左手を離して、正しくお箸を持つ
なお、左利きの場合は箸置きを右側に置いて、箸の向きを変えたあと、右利きの場合と逆にして行なってください。
続いて、お箸の正しい持ち方は以下の通りです。
上のお箸:親指、人差し指、中指の3本で箸を軽く挟み、鉛筆のように持ちます。持つ位置は、箸先から2/3あたりが基本です。
下のお箸:薬指と小指で箸を支えるように持ち、動かさないよう固定します。
また、お箸を使う時は基本的に下を動かさずに、上の箸のみを動かします。
お箸のマナー違反「嫌い箸」とは?
和食には、「嫌い箸(きらいばし)」と呼ばれるマナー違反の箸使いが多数存在します。その多くは無意識のうちにやってしまいがちですが、次のようなお箸の使い方をしていないか一度確認してみましょう。ここでは、代表的な嫌い箸の例をご紹介します。
・迷い箸:どの料理を食べようかと、皿の上で箸先をあちこち動かすこと
・涙箸:箸の先から汁をたらすこと
・指し箸:箸を使って人や物を指すこと
・持ち箸:箸を持ったまま食器などを持つこと
・刺し箸:料理に箸を突き刺して食べること
このほかにも、食べ物を箸から箸へと渡す「渡し箸」、箸を逆さにして持つ「逆さ箸」、箸先を口で舐める「ねぶり箸」など、様々な種類があります。
おしぼりと懐紙の基本的な使い方とマナー
「おしぼり」や「懐紙(かいし)」は日本ならではの文化ですが、それぞれ基本的な使い方やマナーがあります。
おしぼりの使い方
「おしぼり」は手を拭くためのもので、特に男性で顔や首を拭いてしまう方がいますが、マナー違反となりますので注意しましょう。テーブルや食器の汚れを拭くのも同様です。
あくまで手先を清潔に保つために使うものとして、丁寧に両手を軽く拭くのが正しい使い方です。
また、おしぼりを使い終わったあとは拭いた部分を内側にたたんで元の位置に戻します。
懐紙の使い方
「懐紙」とは、和食や茶道の場などでよく利用される小さな和紙で、ティッシュのように一枚ずつ取って使います。
使い方としては、口元や箸の汚れを拭う、魚の小骨や果物の種を口から出すときに口元を隠す、徳利からたれた水滴を拭く、受け皿の代わりに添えるなど様々です。
懐紙を上手に使うことで、控えめで上品な印象を与えることができます。
器の扱い方について

和食では、器を手に持って食べる文化が根付いています。ただし、すべての器を持ってよいわけではありません。
手に持って食べてもよい器
和食では、手のひらに収まる程度(約15cm以下)の器であれば、基本的に胸元まで持ち上げて食べることができます。
ごはん茶碗や汁椀、小鉢皿や小皿などのほか、鰻重の重箱やカツ丼のどんぶりといった器も手で持って食べてよいとされています。
また、お寿司やお刺身をいただく際の醤油皿など、汁がこぼれやすいものもOKです。
手で持って食べてはいけない器
お刺身や焼き魚、揚げ物といった主菜や大皿、中皿など、料理の内容や盛り付けに配慮すべき器は、持ち上げずにいただくのがマナーです。
食べにくい場合は取り皿を使って、少量ずつ移してから手に持って食べるようにしましょう。
会席料理の正しい食べ方について
食事会で出されることが多い日本料理「会席料理」は、運ばれてきた順に箸をつけるのが基本です。ここでは、会席料理の正しい食べ方を順番別にご紹介します。
1.先付け
食事の最初に出される「先付け」は「お通し」とも呼ばれ、前菜のことを指します。
旬の素材を使った料理が多く、椀や小鉢に入っている場合は持ち上げていただきましょう。串物は一つずつ箸で押さえて、串を引き抜いてからいただくようにしてください。
2.吸い物
「吸い物」は、すまし汁や、うしお汁などの汁物のほか、土瓶蒸しが出されることがあります。
器に蓋がついている場合は、目上の人が先に蓋を取るまで待つのがマナーです。外す際は音を立てないように注意し、蓋を裏返して、お椀が右側にある場合は右、左側にある場合は左に置きます。食べ終わったあとは、蓋を元通りに被せておきましょう。
3.向付け
向付けとは、お刺身・お造りのことです。盛り付けを崩さないようにするのがポイントで、複数の種類がある場合は手前から奥の順に食べていきます。一般的に手前が淡白な魚、奥には脂がのった魚が盛り付けられています。
また、わさびは醤油に溶かさず、刺身の上に少量乗せてから醤油に直接つけていただくのが基本マナーです。
4.焼き物
「焼き物」は尾頭付きの魚や海老、帆立が提供されることが多く、特に骨付きの焼き魚は食べ方に注意する必要があります。尾頭付きの場合はひれを外して、頭の方から尾にかけて身を食べていきます。魚をひっくり返すのはマナー違反となるので、反対側を食べる際は骨を外して下の身をいただきましょう。
また、骨や頭などの残骸が目立たないように「懐紙」を使って隠すと、きれいな食べ方となります。
焼き物は殻を外す時などに手を使ってもよいとされています。汚れた手はおしぼりで拭きましょう。
5.揚げ物
「揚げ物」は一般的に天ぷらのことを指し、盛り付けが崩れないように手前から食べるのが基本になります。つゆが垂れ落ちてしまわないように、天つゆの器を手に持って口に運ぶとよいでしょう。
6.蒸し物
「蒸し物」といえば茶碗蒸しが一般的で、ほかには酒蒸しがあります。蓋を静かに取って、スプーンか箸で音を立てずに食べるのがマナーです。なお、だし汁と具材は混ぜて食べてもマナー違反にはなりません。
7.ご飯・止め椀・香の物
コースの締めとして登場するのが「ご飯」、「味噌汁などの汁物(止め椀)」、「漬物(香の物)」です。これらは「主食」としてではなく、「しめの一膳」として位置づけられています。お酒の追加注文はここでストップするのがマナーです。
8.水菓子・甘味
最後にデザートとして提供されることがある「水菓子」や「甘味」は、果物や和菓子、ゼリー、寒天といった、さっぱりとしたものが中心です。
皮が付いた果物は、剥いた皮を折りたたむ、種と一箇所にまとめるなど、きれいに食べることを心がけましょう。和菓子と抹茶の場合は、先に和菓子をいただいてから抹茶を飲みます。
最低限のマナーを身につけて和食を楽しもう

和食のマナーは、決して堅苦しい作法を強いるものではなく、料理をよりおいしく味わい、一緒に食事する相手への思いやりを形にしたものです。
これから和食の席に臨む方は、ぜひ今回ご紹介したポイントを参考にしながら、丁寧な振る舞いとともに、日本の美しい食文化を存分に味わってください。

コーチングは現在、ビジネスの場面をはじめ、プライベートの場面においても広く用いられるようになってきています。
それは、コーチングが人の「強み」を伸ばし、行動化をサポートする新しいコミュニケーションの技術であることが理由かもしれません。この技術の新しさは、相手の不平や不満という負の感情さえも、建設的な力への転化が可能であることです。
さらに注目したい画期的な効果として、コーチングが「違い」を活かし合う創造的なコミュニケーションの手法であることから、
相性や性格、価値観が合わない相手との対応力を向上させることも可能にしてしまう点です。
結果として、自分のコミュニケーション能力の飛躍的な向上やリーダーシップなどの幅を広げることに役立てられます。
コーチングは「自分らしさ」も「相手らしさ」も大切にし、「お互いを高め合う」コミュニケーションの手法ともいえます。
老若男女、職種などに関係なく学習し、さまざまな場面で活用できる技術です。